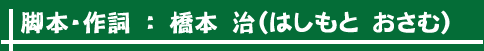
1948年(昭和23) 東京生まれ。’67年(昭和42)に東京大学文科?類に入学。国文科では「歌舞伎」、その後、美術史
学科で「北斎」を専攻。卒論は『鶴屋南北論』であった。東大紛争真っ只中の’68年(昭和43)、東大駒場祭のポスターを
描き、「とめてくれるなおっかさん 背中の銀杏が泣いている 男東大どこへ行く」 のコピーとともに、一躍、時代の寵児
として脚光を浴びる。’73年(昭和48)に大学卒業後は、イラストレーターとして活動するが、’77年(昭和52)、当時の常
識では異次元の生き物にも感じられた”男性化した元気ハツラツな女子高生” と”少女的な男子” たちが躍動する小説
『桃尻娘』を発表。全編を貫く女子高生のしゃべり言葉は「桃尻語」として爆発的な人気を集めた。講談社小説現代新人賞
佳作となった本作を境に文筆業へと転身。以後、小説・評論・歴史書・古典文学の現代語訳・エッセイ等で精力的な執筆
活動を展開。その他にも、占い本や編み物のハウツー本、美術書、画集等々、<橋本ワールド>の広がりと深遠さは計り
知れない。その世界から発信された「流行」は、単なるブームに止まらず、例えば、前述の「桃尻語」などは、彼の古典文学への造詣の深さと愛情に裏打ちされた『桃尻語訳 枕草子』として結実。『窯変源氏物語』、『双調平家物語』などと共に、古典文学の大胆な現代語訳や二次創作は独創的で創意に富み、「新たな文学ジャンル」と呼ぶにふさわしい輝きを見せている。『ひらがな日本美術史』、『上司は思いつきでものを言う』、『小林秀雄の恵み』、『巡礼』、『橋』、『リア家の人々』など、小説、評論、随筆等の著書多数。戯曲には、『義経伝説』、『月食 RAHU』、『平成絵草子 女賊』などがある。

