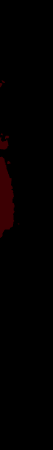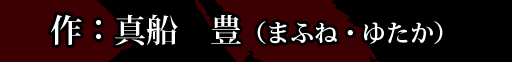

1902年(明治35)福島県安積郡福良村(現郡山市湖南町)生まれ。
一旦は北海道に養子に出されるが、上京して早稲田実業、早稲田英文科に学ぶ。アイルランドの劇作家シングの『アラン島』に感動し、『水泥棒』(1925)『寒鴨』(1927)などの一幕物の戯曲を発表するが、ストリンドベリの「人間修行」に影響され、大学を退学して農民運動に入る。その後、上京して新聞記者となるが、劇作に集中するため1ヶ月で退社し、貧困と妻の病気に苦しみながらも『劇文学』に発表したのが『鼬』(1934)である。みずから演出を買って出た久保田万太郎の熱意もあって、『鼬』の初演は絶賛の的となり、新人の真船豊は一躍劇壇の寵児と目される。『太陽の子』『裸の町』『見知らぬ人』(1936)、翌年の『遁走譜』(1937)を発表し、前二作は同年映画化もされるほどであった。この時期には放送劇の分野にも意欲を示し、『なだれ』(1935)、『激流』(1939)など、ラジオドラマ史上を飾る傑作を残している。
第2次世界大戦後、中国大陸から引き揚げた後はファルスへの傾斜を深め、『中橋公館』(1946)、『黄色い部屋』(1948)、『赤いランプ』(1954)、『善光の一生』(1963)など、諦観を交えた人間風刺劇へ向かった。
その作品は久保田万太郎、千田是也などの推奨者により、発表を待って新劇や新派劇によって上演され続けた。
小林秀雄や吉田健一の愛した小説や評論もある。1977年(昭和52)8月3日没。
一旦は北海道に養子に出されるが、上京して早稲田実業、早稲田英文科に学ぶ。アイルランドの劇作家シングの『アラン島』に感動し、『水泥棒』(1925)『寒鴨』(1927)などの一幕物の戯曲を発表するが、ストリンドベリの「人間修行」に影響され、大学を退学して農民運動に入る。その後、上京して新聞記者となるが、劇作に集中するため1ヶ月で退社し、貧困と妻の病気に苦しみながらも『劇文学』に発表したのが『鼬』(1934)である。みずから演出を買って出た久保田万太郎の熱意もあって、『鼬』の初演は絶賛の的となり、新人の真船豊は一躍劇壇の寵児と目される。『太陽の子』『裸の町』『見知らぬ人』(1936)、翌年の『遁走譜』(1937)を発表し、前二作は同年映画化もされるほどであった。この時期には放送劇の分野にも意欲を示し、『なだれ』(1935)、『激流』(1939)など、ラジオドラマ史上を飾る傑作を残している。
第2次世界大戦後、中国大陸から引き揚げた後はファルスへの傾斜を深め、『中橋公館』(1946)、『黄色い部屋』(1948)、『赤いランプ』(1954)、『善光の一生』(1963)など、諦観を交えた人間風刺劇へ向かった。
その作品は久保田万太郎、千田是也などの推奨者により、発表を待って新劇や新派劇によって上演され続けた。
小林秀雄や吉田健一の愛した小説や評論もある。1977年(昭和52)8月3日没。