|
|
シス・カンパニー公演 火のようにさみしい姉がいて |
| SIS company inc. のプロデュース作品のご紹介 | |
|
公演概要 |
東京公演 |
大阪公演 |
キャスト・スタッフ |
HOME
本公演は、10/13(月祝)に全公演の幕を下ろしました。 ご来場、誠にありがとうございました。 |
|
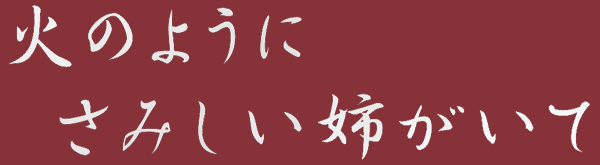 |

作:清水邦夫×演出:蜷川幸雄 と言えば、1960年代末の活動初期から行動を共にし、その共同作業で多くの熱狂を生み出してきた伝説の2人です。いつの頃からか「ゴールデンコンビ」と形容されるようになった2人ですが、世の中に送り出してきた数多くの名作舞台は、時代を超えて幾度となく上演を重ねながら、決して一つのイメージに留まることなく、毎回新たな生命を宿すかのように進化し続けてきました。
時に詩的で美しく、時に挑発的で激しく、時に滑稽で軽やか・・・・。蜷川幸雄は虚構と現実の狭間を漂うかのような清水邦夫の劇言語と常に格闘しながら、自身の演劇的ダイナミズムと清水邦夫の感性を融合させ、舞台上に、<ゴールデンコンビ>ならではの、唯一無比の世界観を提示してきました。 常に急進的で、抒情を称えつつアグレッシブな疾走感に満ちた作風の一方で、清水邦夫は、70年代半ばから劇団制にとらわれない形で自身の戯曲上演を進める演劇企画集団「木冬社」を主宰。本年3月に逝去した女優・松本典子と共に、独自の演劇活動を長く展開してきました。本作「火のようにさみしい姉がいて」は、木冬社結成3年目の78年に初演。 その後96年に、清水邦夫自らの演出で再演され絶賛を浴びました。美しく懐かしい記憶の奥にあった故郷が、ある瞬間に恐怖にも似た存在になる・・・・。そんな記憶の迷宮をスリリングに描いた本作は、その後また上演の機会はなく、<伝説的な戯曲>として人々の脳裏に刻まれてきた作品でした。 かつて、蜷川幸雄は、「清水邦夫全仕事」という作品全集に、清水邦夫の資質は蜷川自身がかかわっていない作品の中に結実している、だからこそ「木冬社」での仕事は清水邦夫そのものだ、という趣旨の文章を寄せていました。長く創作活動を共にしてきた劇作家と演出家の間に、未だ向き合うことのなかった作品が存在したこと自体、私たちには新鮮な驚きなのですが、同時に、なぜ今、これまで手がけなかった「清水そのもの」の作品に向き合うことになったのか等、新たな興味が次々と生まれてきます。 多くの意味で、本公演は、<新たな伝説の始まり>と言えるのかもしれません。  そして、もうひとつ、その<新たな伝説>を確信させるのが、すでに大きな話題を呼んでいる2人のトップ女優:大竹しのぶ×宮沢りえ の舞台初共演です。映像では、2011年に放映されたNHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国』で、北政所(大竹)、淀(宮沢)役での共演はあるものの、<ナマの舞台での初激突>は、演劇ファンならずとも驚きの大きなニュースとして配信されました。 これまでも大竹、宮沢それぞれの主演舞台の演出を手がけ、それぞれの魅力を存分に知り尽くしている蜷川ですが、自身が初めて手がける清水作品に大竹、宮沢を配したことにも、その決意の大きさがうかがえます。 そして、大竹、宮沢の狭間に立ち、虚構と現実の狭間で翻弄されるような「男」を演じる段田安則 をはじめ、山崎一、平岳大、満島真之介、西尾まり、中山祐一朗、市川夏江、立石涼子、新橋耐子 ら強力なキャスト陣の存在が、迷宮の出入り口のような鏡の奥から真実をえぐり出すような物語に、多面的で強靭な表情を加味していきます。
そして、もうひとつ、その<新たな伝説>を確信させるのが、すでに大きな話題を呼んでいる2人のトップ女優:大竹しのぶ×宮沢りえ の舞台初共演です。映像では、2011年に放映されたNHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国』で、北政所(大竹)、淀(宮沢)役での共演はあるものの、<ナマの舞台での初激突>は、演劇ファンならずとも驚きの大きなニュースとして配信されました。 これまでも大竹、宮沢それぞれの主演舞台の演出を手がけ、それぞれの魅力を存分に知り尽くしている蜷川ですが、自身が初めて手がける清水作品に大竹、宮沢を配したことにも、その決意の大きさがうかがえます。 そして、大竹、宮沢の狭間に立ち、虚構と現実の狭間で翻弄されるような「男」を演じる段田安則 をはじめ、山崎一、平岳大、満島真之介、西尾まり、中山祐一朗、市川夏江、立石涼子、新橋耐子 ら強力なキャスト陣の存在が、迷宮の出入り口のような鏡の奥から真実をえぐり出すような物語に、多面的で強靭な表情を加味していきます。新たな伝説の誕生の瞬間に、是非ご期待ください! 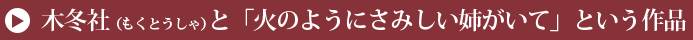
「木冬社」は、1976年(昭和51)、劇作家・清水邦夫が、俳優・松本典子、山崎努らと共に結成した演劇企画集団。
劇団組織体制をとらず、清水邦夫自ら書き下ろした戯曲を、公演ごとに俳優やスタッフが参加する"開かれた形"で上演することを主眼とした。 第1回公演『夜よおれを叫びと逆毛で充す青春の夜よ』で、清水は第11回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。 続いて、木冬社第2回公演として、77年(昭和52)に初演されたのが、『楽屋〜流れ去るものはやがてなつかしき〜』である。 この戯曲は、その後、木冬社でも幾度となく再演が重ねられたが、当時から現在に至るまで、他劇団やプロデュース公演、学生演劇等々の手で、いつも日本の必ずどこかで上演されていると言っても過言ではないほどの人気を博している。シス・カンパニーでも、2009年(平成21)に、演出:生瀬勝久、出演:小泉今日子、蒼井優、村岡希美、渡辺えり の顔合わせで上演し注目を集めた。 そして、78年(昭和53)に、木冬社第3回公演として、紀伊國屋ホールにて上演されたのが、本作『火のようにさみしい姉がいて』である。初演時の演出は秋浜悟史が務めている。 初演キャスティングは、今回、大竹しのぶが演じる<中ノ郷の女>には演劇集団円の岸田今日子、段田安則演じる俳優の<男>には山崎努が扮し、宮沢りえの<妻>は松本典子が演じ、その年の「演劇ベスト5」に選ばれている。 その後、再演を熱望する声が多かったにもかかわらず実現まで実に18年の歳月を要し、紀伊國屋サザンシアター開場記念/木冬社公演として再演されたのは、木冬社結成から20年を迎えた96年(平成8)であった。 再演の演出は清水邦夫自身が手がけ、台本にも清水自身の手が多少加えられ、「火のようにさみしい姉がいて'96」というタイトルで上演された。 再演キャスティングは、初演で<妻>を演じた松本典子が再演では<中ノ郷の女>に扮し、その圧倒的な存在感を示した。そして、<男>は、清水邦夫と60年代末から70年代初頭にかけ演劇活動を共にしていた蟹江敬三、<妻>は、劇団民芸で松本典子との共演も多かった樫山文枝が演じ、3人の関係性を初演以上のスリリングな緊迫感をもって舞台上に描き、絶賛された。 その後、本作上演の機会は長らくなく、それゆえに、<幻の名作>とさえ呼ばれていたが、再演から再び18年の時を経て、今回の蜷川幸雄演出での上演が実現することとなった。 木冬社は、もちろん、この第3回公演以降も精力的に清水作品を発表し続けてきたが、90年代からは、清水オリジナル作品に加え、小説の劇化にも取り組み、『愛のかたちを探る週末の一幕劇集』としてルイ・フィリップ作品を劇化・演出。94年(平成6)には、アゴタ・クリストフ作『悪童日記』の劇化・演出に挑み、同年上演の『わが夢にみた青春の友』と両作品の成果に対し、木冬社には第29回紀伊國屋演劇賞団体賞が授与された。 
開演を数分後に控えた、とある劇場の楽屋。化粧前の鏡の前で、主演俳優(段田安則)がセリフを返しながら出番を待っている。しかし、男の目は鏡の奥の別世界を見ているかのようだ。
そこに、男の妻(宮沢りえ)が入ってくる。精神的に疲れ切った男と妻の会話は、何やら現実と芝居の世界が混同し、 どちらがどう合わせているのかはわからないほどだ。 仕事にも人生にも行き詰まった夫婦は "転地療養"と称し、20年ぶりに日本海に面した男の雪国の故郷に旅立った。 到着後、実家に向かうバス停を尋ねるために立ち寄った理髪店には誰もいない・・・。 誰もいない理髪店の鏡の前で、男は誤って、鏡の前にあった髭剃り用のシャボンのカップを割ってしまう。 次の瞬間、理髪店の女主人(大竹しのぶ)や、得体の知れぬ客たちが次々に現れて、本気なのか演技なのかわからないほどの脅迫的な言葉で2人を取り囲む。そうこうするうちに、どんどん男の過去に強引に入り込んできて・・・・。 鏡の前で、今、語られている男の過去は現実なのか、虚構なのか? 鏡に映された姿の何が本当で何がウソなのか・・・? 判然としなくなった妻は、真実を追求しようと敢然と立ち向かうのだが・・・・。 |
|




